「勉強しなさい」は逆効果?やる気を下げない声かけの考え方
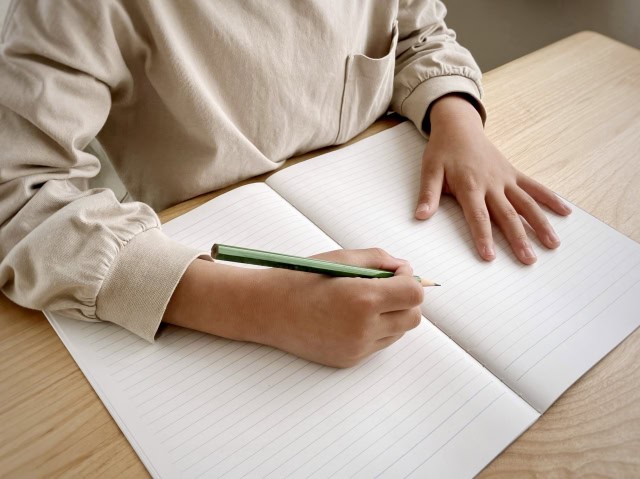
こんにちは。教室長の丹下です。
10月になりました。
2学期初めての定期テストをすぐに控えているお子さんも多いのではないでしょうか?
2学期は1学期よりもぐっと難しくなるとき。どの学年も平均点がガクッと下がる傾向にあります。
そして、少しずつ「差」が出始めてくるころです。これからのテスト勉強はより一層、量・質ともに良くしていかなければいけませんね。
前回、テスト課題は3回繰り返しやりましょうというお話をしました。(まだご覧になってない方は、ぜひこちらもご覧ください。→「学校のテスト課題、どれだけ大切なの?」)
今回は、「暗記が必要な単元のテスト課題のやり方」に関してお話します。

自分の教室の生徒を見ていると、社会や理科などの暗記科目のワークをやるとき、
教科書を隣に置いている子がすごく多いです。
一問ずつ解くたびに、教科書をパラパラめくり調べながら答えを埋めているのです。
「なんでそういうふうにやるの?」と聞くと、
「全然覚えていないから。」「×ばっかで出すの嫌だから。」と返ってきます。
しかしこのやり方には、問題点が2つあります。

1つ目は、時間がかかりすぎることです。
テスト課題はだいたいどれも20~30ページくらいあります。そのなかで一問ずつ教科書で答えを探しながらやっていくと、終わるころにはテストの前日、などギリギリになって結局解き直しができなくなってしまうことが多いです。
2つ目は、自分が忘れていたもの、覚えられていないものがわからないということです。
教科書で調べながら1つずつ埋めている子は、だいたい全部埋め切れたら、普通に丸つけをします。終わったワークを見ると、いかにも全て正解できているように見えます。
これだと、あとで解き直しをするときに、「自分がどこを覚えられていなかったのか」がわからず、どこを中心に再度勉強していかなければいけないのかわからなくなってしまいます。

この2つを解決するために、
教科書で調べながらやるのはやめましょう!
ワークは×だらけで出しても良いです。
となりに解説を写したり、解き直しのノートを一緒に出したりすれば、「テスト勉強一生懸命やったんだな」と伝わります。
×だらけで出すのがどうしても嫌なら、教科書を一通り読んだ後、教科書を閉じてワークに取り組むようにしましょう。
また、それでも調べながらやりたいという場合は、調べたものには色ペンなどで印をつけておくなど、自分も先生もどれがわからなかった問題なのかが後で見てわかるようにしておきましょう。
前回もお話した通り、テスト課題の1回目は自分が苦手なところ、わからないところを見つけるためのものです。
わかるようにする、覚える作業は2回目以降に行うことです。
このことを忘れずに、ぜひテスト勉強に臨んでほしいと思います。
お問い合わせ・無料体験申し込みはこちら