「勉強しなさい」は逆効果?やる気を下げない声かけの考え方
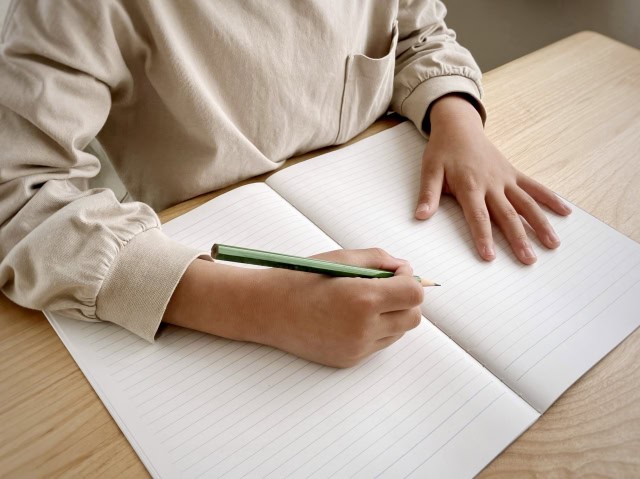
普段の授業に加えて、学校行事や部活などもあり、子どもたちはなかなか忙しいものです。
疲れや忙しさを理由に、帰宅してもダラダラしてしまって勉強に取りかかれない子もいます。また、宿題をやったとしてもそれ以外の家庭学習を全くやらない子もいますよね。
勉強をしてほしいと思えば思うほど
「勉強しなさい!」「子どもなんだから疲れたって言わないの!」「お母さんなんて、あなたよりももっと忙しいよ!」
と言いたくなってしまいがちですよね。
ただ、子どもの疲れや忙しさを否定するのはNGです。
親が自分の気持ちや状況を分かってくれずに頭ごなしに「こうしなさい」「こうしなきゃダメ」といっても、子どもも聞こう!という気にはなりません。
子どもに勉強をしてもらうためのアプローチをする前の下地として、まずは疲れた気持ちや忙しさを理解して寄り添うようにしましょう。

あなたの忙しさは分かっているよ、毎日やることがたくさんあったりして疲れるよね、といったことが伝わったら、時間の使い方を提案しましょう。
その際に、同時に行いたいのが“疲れや忙しさを緩和する工夫”です。
ライフスタイルはご家庭によっても違いますし、年齢、子どもの性格などでも変わってきます。
そのため「これをすれば疲れや忙しさがなくなるよ!」とは言えないのが正直なところ。
実際は、トライ&エラーを繰り返しながら生活リズムを整えていく必要があります。

以前、疲れや忙しさで家庭学習の意欲がわかない、そもそもそこまで勉強時間が取れない、と悩んでいた中学生の子がいました。そこで、生活のサイクルを見直して工夫を行ったら勉強がはかどり、最初は絶対に無理と思っていたレベルの高い学校に合格できました。
今回は、その子の例を紹介させていただきますね。
18:00~帰宅・ダラダラする時間
19:00夕食
20:00お風呂
21:00就寝
4:00起床
4:15~6:15宿題+家庭学習
6:30~朝食・教科書の準備・身支度
7:30登校
ざっくりとこのような生活リズムです。部活の退会が近いと帰宅時間が遅くなったり、テスト前の部活停止では逆に早くなったりしますが、就寝時間と起床時間はいつも変えないようにしていました。

そもそも部活で勉強とは違う方向に頭のスイッチが入ったまま帰ってきて、その後勉強への切り替えが難しいと感じて「それならばいっそのこと、帰宅後はダラダラする時間にして、勉強も学校の準備も一切やらずに、考えずに、すべて朝にまわそう」と考えたそうです。
「最初の1~2週間は起きるのが大変だった」というこの生活リズムには、定着してしまえば帰宅後~寝る前まで勉強のことを考えずにダラダラ過ごせるのでストレスも溜まらずに取り組める、朝の集中力が高い時間に勉強できるので勉強効率も上がる、といったメリットがあります。

ただ、すべての子に最適な方法ではない点には注意が必要です。
子どもによって最適なサイクルや時間の使い方があります。そのため、家族で協力しあい、勉強ができる生活リズムをぜひ見つけてみてくださいね。
お問い合わせ・無料体験申し込みはこちら