1学期のやり残しを明確にしよう
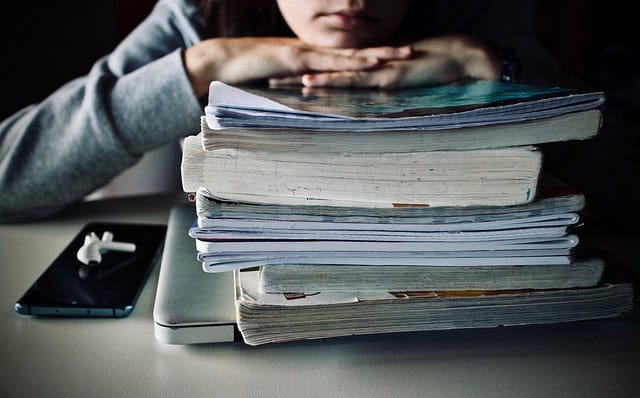
前々回から3回に渡り、「テスト慣れ」についてお話しています。
テスト慣れをするために普段の勉強でやるべき行動は、
「①問題を解く」→「②成果を数字で記録する」
やるべき行動はとてもシンプルです。
今回は、「②成果を数字で記録する」について詳しく解説します。
まだ過去記事をご覧になっていない方はこちらもあわせてご覧ください。
「テスト慣れしているかどうかは普段の問題演習の量で決まる!」

テスト慣れのために「問題を解く=(問題演習をする)」は必ずやるべき行動です。
ですが、問題を解いた後、せっかく解いた問題をそのまま放置してしまったら意味がありません。
必ず、答え合わせ・間違い直しをしましょう。
さらにそこまで出来たらテスト慣れのためにやるべき行動がもうひとつあります。
それが「②成果を数字で記録する」です。

まず答え合わせをしたら、どの問題が×だったのかをワークに書き込みましょう。間違えた問題の問題番号のところに赤でチェックを打つ、などが良いでしょう。
そして「問題を解いた日付」と「何問中何問解けたのか」をワークの一番上に記録しましょう。一度やったことのあるページを解くと、前回と比べてどのくらいレベルアップしたかが分かります。
また、数字の記録を使ったこんな勉強方法もおすすめです。
<用意するもの>
<やり方>
テスト慣れにおいて問題を解いている時に時間を意識できるというのは非常に大切なところです。
この時間感覚がある子とない子とでは、テストの結果に雲泥の差が現れます。

3回にわたって「テスト慣れ」についてお話してきました。
「テストで点数が取れなくて悩んでいる」「とにかく勉強するしかないと思って頑張っているけどテストで結果が出ない」というお子様はたくさんいらっしゃいますが、
「テスト慣れ」という観点から勉強のやり方を見直そう、と考えるお子様はなかなかいません。
この考え方があるだけで周りと大きく差をつけることが出来ます。
あとは行動するのみです。
お子様の行動を、保護者様の目を通して分析し、足りない行動を補填してあげられるような声がけをしてあげてくださいね。
お問い合わせ・無料体験申し込みはこちら