「勉強しなさい」は逆効果?やる気を下げない声かけの考え方
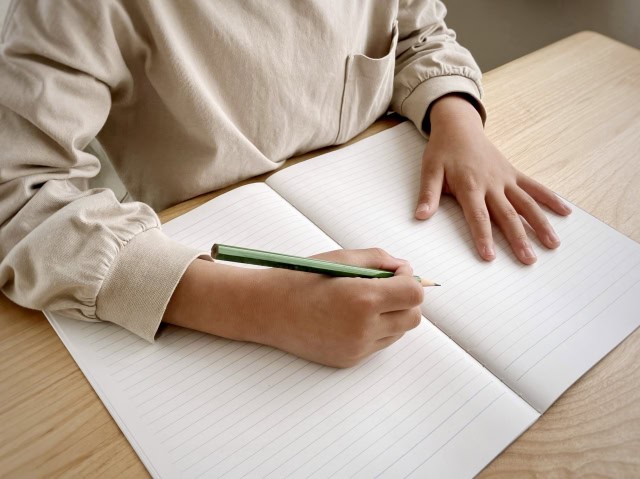
こんにちは!個人指導専門塾の岡田です。
この時期になると、高学年の生徒さんの保護者の方から
「学年が上がって勉強についていけるのかしら・・・?」「中学生に向けて、できるようにならないといけないことって何でしょうか?」といった心配の声を多く受け取ります。
実際、小学校5・6年生になった途端、成績や理解するスピードが急に落ちてしまう子が非常に増えます。

そこで、4年生までの勉強と5・6年生になってからの勉強のイメージを変えていく必要があります。
小学4年生までの勉強は、漢字や語句、各科目の用語や公式などを「覚えていれば」好成績を取ることができました。
一方、高学年になると「今まで覚えてきた知識を組み合わせて複合的に、あるいは総合的に問題を解いていく」方法に変えていかなければなりません。
「覚えるだけで大丈夫」のイメージのまま高学年の単元に触れると、今まではできたのに急に難しくなった!という現象が起こるのです。

例えば、高学年のお子様が取り組む算数の単元ではこういったものが挙げられます。
これらは高学年の生徒さんがつまずいてしまい、それを後々引きずってしまいやすい単元です。
このような単元は
という過程を組み込む必要があります。

そのため、これからの勉強において必要なのは、「問題文に書き込むこと」と「図や表、グラフを自分で作成すること」です。
ただし、すぐに身につけられる習慣ではないため、まずは簡単な作業を習慣にしていくことがポイントです。
まずは、1つの問題に対して、色の違うマーカーを用意し、使い分けて下線を引くというところから始めていきましょう。
例:時速60kmの自動車が2時間進んだ時の道のりは何kmですか?
このように色分けをすることで、ミハジのどれを使えばいいかを色分けされた視覚情報に頼ることができ、読み解きの効率がぐんと上がります。
このような小さな習慣を日々の勉強の中に落とし込んでいくことで、「覚える」勉強から「覚えて思考する」勉強に切り替えていくことができます。
習慣になるまでは、難易度の低い問題で実践していき、まずは「必要なところに線を引く」ことに集中すると良いと思います。
まずは焦らず、できることから習慣にしていきましょう!
お問い合わせ・無料体験申し込みはこちら