「勉強しなさい」は逆効果?やる気を下げない声かけの考え方
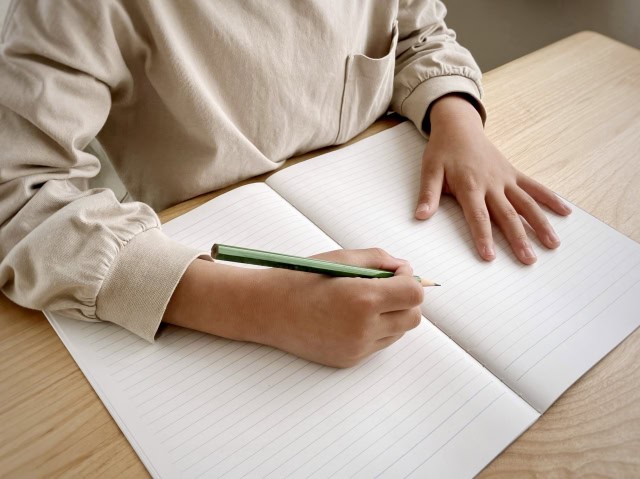
こんにちは、個人指導専門塾の平田です。
前回、学習意欲を高く維持するために
「自己効力感も維持しよう」というお話をしました。
まず、言葉のおさらいです。
「学習意欲」とは、勉強に対するやる気のこと。
「自己効力感」とは、「自分なら出来る!」と自分で自分を信じてあげる気持ち のことです。

勉強する場面において、自信を持てているかということですね。
自己効力感を感じるタイミングは大きく分けて2つあります。
①自分で自分を認めることができたとき
②人に認められたとき
1つずつ見ていきましょう。
①自分で自分を認めることができたとき

例えば、学校でやった数学の文章問題を、その日に家でひとりでやってみたら、
なんとか答えを出すことが出来たとします。
その時に、
「今日習ったのに、こんなに考えないと出来ないなんて。自分は馬鹿だ。」と思うか、
「家でもう一回やって良かった!やれば出来るんだな。」と思うか。
後者の方が良いに決まっています。
次に似たような問題があれば、また全力で挑戦するでしょう。
それに、「また復習をしよう」と思うことができますよね。
これこそ自己効力感です!
それに、自分で自分を認めることができる、ということは
先生や親からの賞賛に頼っていないということです。
自分で自分を高める自立した勉強が出来るようになります。
これは大人になってからも大切な能力ですよね。
ですが、完全に自立するのは難しいもの。
そこで、まわりの大人にも出来ることがあります。
②人に認められたとき

必死にテスト勉強をしていた子ども。
定期テストが返ってきて、得意な英語も苦手な数学も点数が下がっていたとします。
それをみて、どのように声をかけるべきでしょうか。
例えば、「数学はもともとダメなんだし、せめて英語はもうちょっと頑張ろうね。」
と言ってしまうことはありませんか?
得意の英語を頑張ってほしいという気持ちはわかりますが、
わざわざ「数学はダメ」と言う必要はありません。
これでは、子どもに対して「貴方は数学が出来ない」というメッセージを送っていることになります。
ではどうすればいいのか?
それは、点数が下がっていても、ピンポイントで良い所を探してみて下さい。
出来れば、テスト前の本人の頑張りも一緒に褒めて下さい。
数学の簡単な計算問題で丸がついていたら、
「計算問題は全部丸だったね。毎日コツコツ練習したおかげだね。がんばったね!」
その後、次にもっと良い点数を取るための課題を話し合えば良いのです。
自己効力感を高めるということは、「自分ならできる」という
自分で自分を信じることができるということと、冒頭に書かせていただきました。
大事なことは、「こうすれば成功する」という具体的な行動がイメージできることです。
そうすることで、自己効力感を高く保つことができるのです。
何が良かったのか? その行動の部分を認めてあげる、
ぜひ、そんな言葉がけを意識してみて下さい。
お問い合わせ・無料体験申し込みはこちら