「勉強しなさい」は逆効果?やる気を下げない声かけの考え方
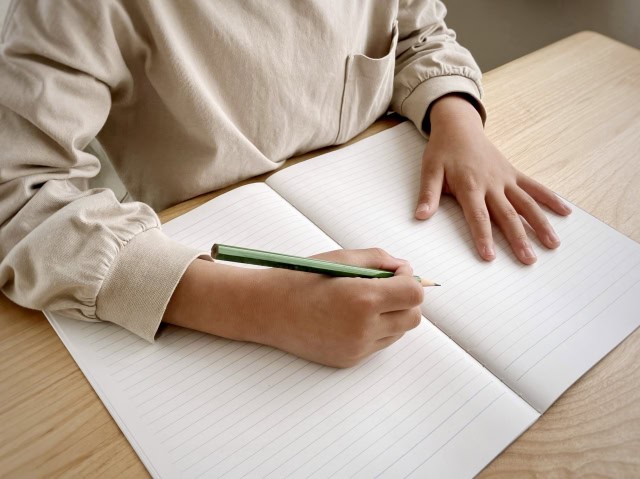
こんにちは。個人指導専門塾の坂口です。
今回は、教室で行っているテスト後の面談の様子をお伝えしたいと思います。
それと合わせて、お子さんに話をするときのコツも一緒にお話し致します。
学校によっては、もう定期テストの返却が行われている頃だと思います。
私の教室でも、定期テストが返ってきた生徒から順に、面談を実施しています。
この面談の目的は、
です。
ポイントは、結果がどうだったかだけではなく、「どういう行動をしてどのような結果になったか」を話すということです。

行動科学では、「結果は行動の積み重ね」であると考えます。
良い結果も悪い結果も、全てはそれまでに積み重ねられてきた行動に起因するということです。
ここで言う「行動」とはテスト勉強、「結果」とはテストの結果(どこが合っていてどこが間違っていたか)のことです。
例えば「何回ワークの解き直しをしたか」「いつテスト勉強をしたか」「テスト期間中一日どのくらい勉強したか」などが行動といえます。
まずは、テスト前の行動がどうだったのかを一緒に確認します。
「テストまでにこの単元は5回解き直しをした」のように具体的な数値まで引き出すのもポイントです。
そして、その行動によって、どのような結果になったのかを確認します。
結果が良かったのであればその行動を次回のテストでも繰り返せば上手くいく可能性が高いということです。
逆に、結果が良くなかったのであればそれまでの行動を見直さなければならないということです。
それを受けて、次回のテストまでに行動をどのように改めていくのか一緒に作戦を立てていきます。

ここで気を付けなければならないのは、生徒が能動的に話が出来るよう誘導するということです。
大人がしゃべりっぱなしなだけでは、せっかく大事なことを話しても頭に残らない可能性が高いです。
なので、大事なことは生徒自身が生徒自身の言葉で言えるような質問の仕方をするということです。
例えば、もう少しで出来そうだった問題をテスト前2回しかやらなかったようであれば、
「何回やった?」「じゃあ何回やるべきだったんだろう?」と聞いてあげると自らの行動を自分の言葉で省みることが出来ます。
ポイントは具体的数値を大人ではなく子ども自身に言わせることです。
人から言われた言葉よりも自分で言った言葉の方が受け入れやすいのは大人も子どもも同じなのです。
そこまで話すことが出来たら、最後に次の目標を決めます。
私は今行っている面談で、ある生徒に、「次回は合計点数を30点アップすることを目標にしよう」と話しました。
30点を5教科で割ると1科目6点。6点とは各テストの大問なら約1問分、小問なら2~3問分です。
このように具体的な数字で表すことにより、子どもは「これだけの問題を解けるようになったら、30点上がるんだ。」と理解してくれます。
もし、「次は30点アップを目指そうね。」で終わっていたら、子どもは何をすれば良いのか分からず、結局、「漠然と問題を解き、答え合わせをする」の繰り返しになってしまいます。
そして、30点アップ出来るかもしれないと思うことが出来たら「がんばって取れそう!」と言ってくれます。ポジティヴな言葉を引き出すのも重要です。

見通しが立っているということはとても大切です。
見通しが立っていないまま勉強するということは、ゴールがないまま走るようなものです。
子どもに限らず、大人も先が見えないのに走り続けるのは「苦」でしかありませんよね。
目標や計画を立てる時は、より具体的な言葉や数字を使用し、子どもがイメージを持ちやすくなるように話しましょう!!
まずは、一緒に話してあげる大人が成功のイメージをつくることが何より大事です。
そうすることで、成功が「グッ」と近くなります!
お問い合わせ・無料体験申し込みはこちら