「勉強しなさい」は逆効果?やる気を下げない声かけの考え方
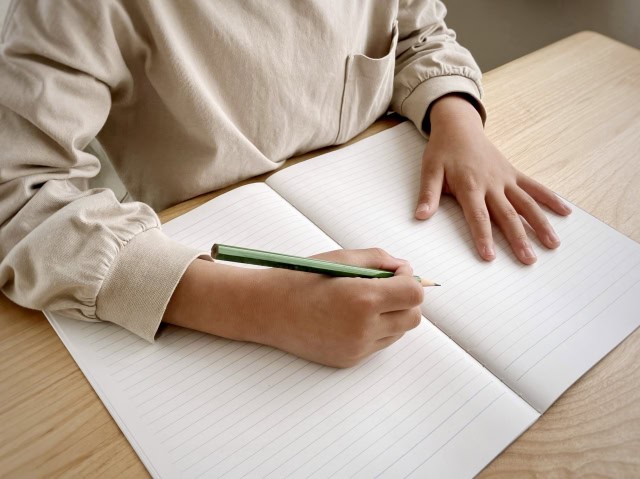
新しい学年が始まる前のこの時期、お子様がスムーズにスタートを切れるよう、保護者の皆様がどのような準備をしてあげるべきかを考えることはとても大切です。
2025年度の教育環境は、従来と比べても変化が著しく、「主体的に学ぶ力」がより一層求められる時代になっています。
学習指導要領の変化やデジタル活用の進展、そして社会全体の変化に適応するために、今こそ家庭での準備が重要になります。
では、新年度に向けて、具体的にどのような準備をしていくべきなのでしょうか?

新学年が始まると、学習内容は一気にレベルアップします。
特に小学校中学年・高学年では、「考える力」を重視した問題が増え、単なる暗記では太刀打ちできない場面が増えていきます。
そのため、春休みのうちに生活リズムを整え、学習習慣を確立しておくことが大切です。
・毎日決まった時間に机に向かう習慣を作る
・朝の時間を活用し、読書や計算練習を取り入れる
・長時間ダラダラと勉強するのではなく、「短時間集中型」の学習を意識する
特に「短時間集中」は、近年の教育で重視されている「メタ認知力(自分の学び方を理解し調整する力)」を養うのに役立ちます。ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩のサイクル)などを試し、お子様に合った勉強スタイルを確立しましょう。

2025年度は、プログラミング教育やタブレット学習がより一般化し、子どもたちが「情報を正しく扱う力」を求められる場面が増えます。
学校の授業でもICT機器を使った学習が進み、調べ学習やプレゼンテーションの機会が増えていくでしょう。
・正しい情報の見分け方を学ぶ(ネット上の情報がすべて正しいとは限らないことを伝える)
・タイピングの基礎を身につける(検索力の向上につながる)
・オンラインでのマナーや安全性について話し合う(SNSやゲームとの付き合い方を考える)
学習のためのデジタル活用は便利ですが、過度な依存を防ぐためにも、「目的を持って使うこと」を意識させることが大切です。

2025年度以降の教育では、「正解を出す力」よりも「自分の考えを持ち、説明できる力」がより重視されていきます。これは、学力だけでなく、社会で生きる力としても求められるスキルです。
・日常の出来事について親子で話し合う(ニュースや学校の出来事など)
・読書を通じて「なぜ?」を考える習慣をつける
・自由記述の問題に慣れる(感想文や意見文を書かせる)
最近のテストでは、「なぜそう考えたのか」を説明させる問題が増えています。親子の対話を通じて、考えを言葉にする練習をすることが有効です。

学年が上がるにつれ、勉強だけでなく生活面でも「自分で管理する力」が求められます。
時間管理や目標設定の習慣をつけることで、学習効率も向上します。
・学校の持ち物を自分で準備させる
・春休みの間に簡単な「目標」を立てる(「毎日10分読書」など達成しやすいもの)
・できたことを記録し、達成感を味わう(シールを貼る、チェックリストを活用する)
自己管理力は、将来の受験勉強や社会生活でも大きな武器になります。
学年が上がると、新しい友達との関係づくりやクラスの変化に適応する力が求められます。
特に最近では「コミュニケーション力」や「共感力」が大切になってきており、人間関係のストレスをうまく乗り越える力も重要です。
・相手の話を最後まで聞く練習をする
・トラブルが起きたときの対処法を考えておく(「嫌なことをされたらどうする?」など)
・人間関係で困ったときの相談先を確認する(先生、親、スクールカウンセラーなど)

2025年度の教育では「ウェルビーイング(心の健康)」も重視されているため、子どものメンタル面のサポートも欠かせません。
新年度の準備は、単に勉強を進めるだけでなく、生活習慣の見直し、デジタルリテラシー、思考力、自己管理力、人間関係スキルなど、幅広い視点で考えることが重要です。
2025年度は、単なる知識の詰め込みではなく、子どもが「主体的に学ぶ力」を身につけることが求められる時代です。
新学年に向けて、ぜひお子様の「学びの土台」を家庭で整えていきましょう。
お問い合わせ・無料体験申し込みはこちら