「勉強しなさい」は逆効果?やる気を下げない声かけの考え方
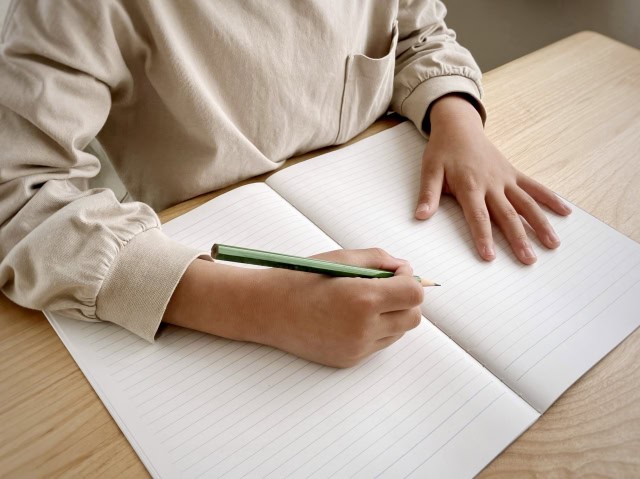
こんにちは。個人指導専門塾の坂口です。
ついに2019年が始まりましたね。
新年を迎え、早速今年の目標を立てたお子さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
まだ目標を立てていない方は、
これからの一年間で何を成し遂げたいか、一年後どんなふうになっていたいかをぜひ考えてみてください。
その目標に向かって正しく行動し続けることが出来れば、必ず未来の自分はレベルアップしています。
そこで今回は「一年後の目標の立て方」についてお話していきます。

目標を立てるポイントは「目標」と「目標達成の手段」を明確に分けて決めることです。
例えば、「小学校の先生になる」という目標があるとしたら、
などの「手段」を考えることが出来ますが、
一年後の目標を立てる場合も同じです。
目標を達成するために何をいつまでに実行しなければならないのかをできる限り具体的に設定します。

例えば、今、中学2年生のお子さんが一年後の目標として「△△高校の合格圏内に入る」という目標を立てたとしたら、
合格圏内に入るための偏差値と現在の偏差値を比べる等して、実力とのギャップを確認し、
そのうえで目標達成のための「手段」を決めていきます。
「手段」なので、具体的な行動を考えましょう。
計算問題を解く、という手段にするのであればどの教材を使うのかも決めておくとすんなり実行にうつれます。

特に直近の行動目標なので今すぐ実現可能なことにしましょう。
その行動のために今持っていないテキストが必要だから買わなくてはいけない、などの条件があると、
行動の前に乗り越えなければいけないステップがまたひとつ出来てしまいます。
大したことに感じないかもしれませんが、それだけで行動にうつらない言い訳になってしまうかもしれません。
手段はすぐにやりやすい具体的な行動を選ぶのがコツです。

また、一年間の行動を年初めに全て決めてしまうのは現実的ではないので、
予測がつきやすい一ヶ月から三ヶ月刻みで計画を立てましょう。
一番大切なのは「実現可能」なことです。
教室でも年初めに新年の目標をひとりひとり立てますが、目標達成の手段として
何となく耳障りの良い言葉を書くお子さんがいらっしゃいます。
例えば、「次のテストは去年よりも早くテスト勉強をはじめる」「もっと計算のスピードをはやくする」などです。
確かに出来るに越したことはないのですが、曖昧な言葉では行動も起こしにくいものです。
上記の内容を具体的にするとしたら、
「3学期の定期テストは3週間前にテスト課題をやりはじめて10日前には課題を一周やり終える。」
「1月は宿題とは別に、学校の計算ドリルを一日一ページ解いて、毎日時間を計り、記録する。」
となります。
決めて満足してしまうような曖昧な行動目標になっていないか、決めた後に厳しくチェックしましょう。
これは結局、目標を立てている自分、理想の自分(「こうだといいなぁ」という願望)を思い描いているだけに過ぎません。
これではいつまで経っても進展はせずに、
「この一年何もやってない。」ということになってしまいます。
ゴールに向かいたくても中間地点の場所が曖昧だと、良いコースで走り切ることは出来ませんよね。
それと同じです。
目標を決めたら期限や数値を決めて、必ず手段を明確にしましょう。
結果は行動の蓄積です。
一年後の目標は、その行動を支える軸となってくれますよ。
お問い合わせ・無料体験申し込みはこちら